教授:吉田 昌弘 (YOSHIDA Masahiro)
【専門分野】機能性材料プロセシング、反応分離工学、生物化学工学
自然界に存在する微生物の機能を活かして土壌環境あるいは水環境の汚染修復技術の開発、新しい機能性を有する高分子材料の開発(ドラッグデリバリー、分離材料、CO2削 減、将来に向けて新技術を提供するマイクロカプセル)、新しい電子材料の接着材(人体に有毒な鉛を含まない接着ガラス)に関する研究を行っています。これらはプロジェクト研究や民間企業との共同研究という形で推進されております。バイオテクノロジーや複合材料プロセシングを通して、社会の役に立つ新 技術の創出、環境対策そしてエネルギー有効利用という社会のニーズに応え、応用開発を目指しています。
1. 新規機能性マイクロカプセルおよびエマルションの開発
マイクロカプセルとは、球体直径がマイクロサイズ程のきわめて微小な容器で、化学的または、物理的手法によってつくられます。一般にカプセルの中に閉じ込める物を「芯物質」といい、カプセルの表面を「カプセル壁材」と言います。芯物質をカプセル壁材によりカプセル化することで以下のような効果が得られます。
2. 鉛を含まない(無鉛)電子材料用接着剤の開発
現在市販の封着加工ガラスは、主組成が酸化鉛(PbO)の低温融解性を活かしたPbO-B2O3系 (鉛ガラス)が中心です。しかしながら、鉛は人体に摂取されると造血酵素障害、赤血球中に変性血球の増加、ヘモグロビンの減少、脳中枢を犯して痴呆症を生 ずるといわれており、その有毒性が問題となっています。さらに、封着・封止材として鉛ガラスを使用した電子部品が廃棄された場合、酸性雨により鉛が地下に 浸透し、土壌汚染、地下水汚染にもつながるためその有害性が問題視されています。このような社会的背景から、これまでの様々な電子部品に使用されている鉛 を含む封着加工ガラスと代替可能な無鉛封着加工ガラス(鉛フリーガラス)の開発が現在緊急の課題となっています。
本研究開発は電子デバイスの必須行程となっている封着・封止を行うための接着ガラス(封着加工ガラス)に関する研究開発です。封着加工用ガラスはエレクトロニクス産業を中心に用いられており、電子デバイスの様々な接合を行う上で極めて重要な材料です。その主な用途は、回路のハイブリッド接合、シリコン半導体、PDP(プラズマディスプレイパネル)基盤などの封着材として数多くの電子部品に適用されています。


研究室の特徴
我々の研究室では、材料プロセシング・環境・バイオテクノロジーに関する研究開発を行っています。材料プロセシングに関する研究開発では、新しい機能性を有した高分子材料(ドラッグデリバリー、分離材料、エネルギー有効利用、将来に向けて新技術を提供するマイクロカプセル(マイクローダーの微小容器))や新しい電子材料の接着剤(人体に有毒な鉛を含まない接着ガラス)に関する研究を行っています。環境・バイオテクノロジーに関する研究開発では、自然界に存在する微生物の機能を活かした土壌環境あるいは水環境の汚染修復技術の研究に取り組んでいます。さらに、癌発現の異常タンパク質の検出、再生医療用の新しいゲル素材を開発するための医療工学にも取り組んでいます。
これらの研究開発は、化学工学的なアプローチを駆使し、プロジェクト研究や民間企業との共同研究という形で推進されております。新しい材料プロセシング、新しい環境対策技術、バイオテクノロジー技術を通して、社会の役に立つ新技術の基礎研究から応用研究まで幅広く展開しております。
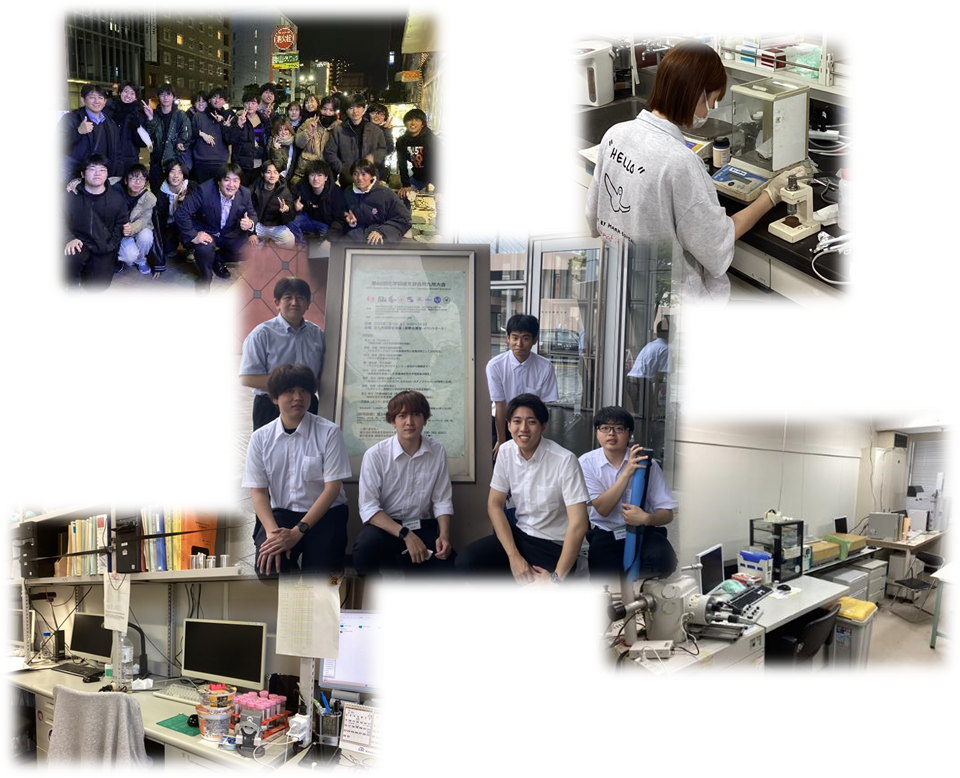
教員紹介
| 職名 | 教授 |
|---|---|
| 電話番号 | 099-285-8526 |
| myoshida@cen. (末尾に、kagoshima-u.ac.jp を付加して下さい) | |
| 担当授業 | 化学工学量論, 機器分析基礎, 基礎有機化学 |
| 研究者総覧 | 鹿児島大学研究者総覧(研究テーマ、業績など) |